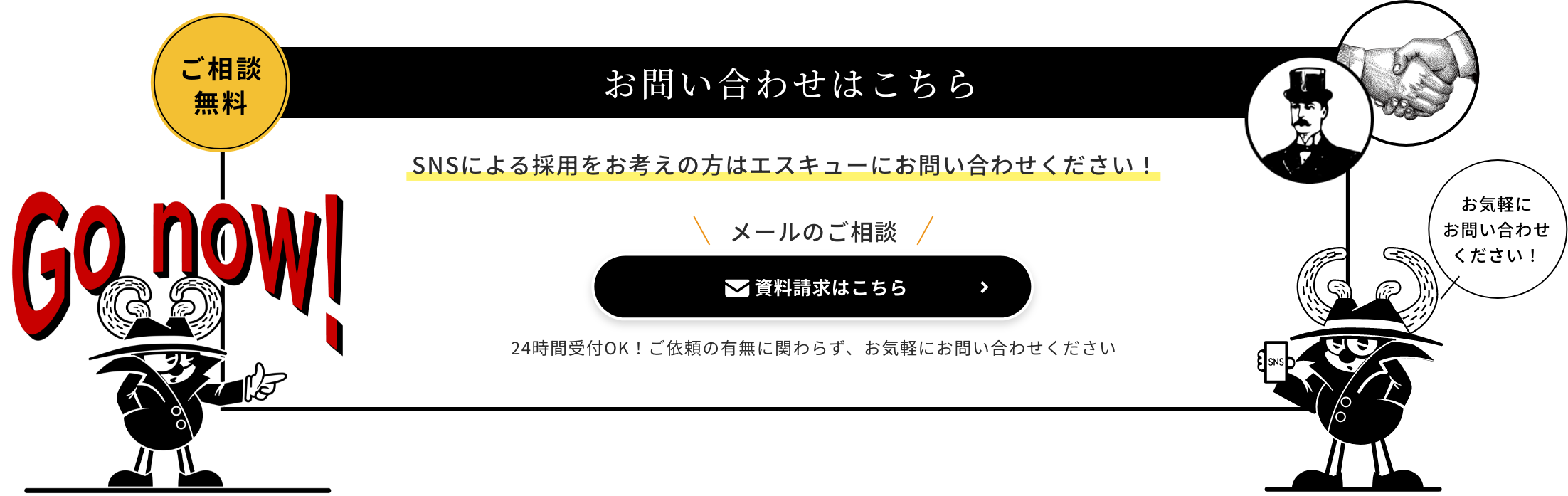ブログ
新卒採用×SNS活用の成功事例|Z世代に響く戦略と実践方法を徹底解説
新卒採用市場は年々変化を遂げており、特にZ世代と呼ばれる若年層へのアプローチには、従来の求人広告や就職情報サイトだけでは限界が見え始めています。そうした中で注目を集めているのが、企業のカルチャーやリアルな日常をダイレクトに届けられるSNS採用です。
企業のSNSアカウントを通じて、自社の魅力を発信し、就活生との自然な接点をつくるこの手法は、採用活動の在り方を大きく変えつつあります。実際に「SNSで見て興味を持った」「TikTokの動画で親しみを感じた」といった声が、若年層の応募動機として増えているのが現状です。
本記事では、**「新卒 採用 SNS 事例」**というキーワードを軸に、SNS採用の基礎から成功事例、活用のポイント、プラットフォームごとの違いまでを詳しく解説します。東京都渋谷区でSNS採用支援サービスを提供する「エスキュー」が、これまでの実績と知見をもとに、新卒採用を成功に導くための実践的なヒントをお届けします。

目次
新卒採用におけるSNS活用の重要性
Z世代の求職者にリーチするためのSNSの役割
近年の新卒採用市場において、Z世代と呼ばれる若年層はSNSを主たる情報収集源としています。従来の求人サイトや企業説明会よりも、リアルな企業の雰囲気や価値観に共感できるSNSコンテンツが意思決定に大きく影響します。企業が求職者に対し親しみや信頼感を与えるには、SNSによるストーリーテリングと日常的な情報発信が極めて重要となります。
企業文化を伝える新たな手段としてのSNS
SNSは、企業の文化や働く人々の価値観を可視化できる優れたツールです。Z世代の求職者は、給与や待遇以上に”どんな人と働くか”を重視しており、InstagramのストーリーズやTikTokの動画などで日常の様子を発信することが、企業へのエンゲージメントを高めます。
Z世代の情報収集行動とSNSの親和性
現在の新卒採用ターゲットであるZ世代(1996年以降生まれ)は、情報収集手段としてGoogle検索よりもSNSを活用する傾向が顕著です。企業名を検索する際も「Instagramで探す」「TikTokで雰囲気を見る」といった行動が一般化しており、企業情報・社員の雰囲気・社風など、文字ではなく“映像や感覚”での理解を重視しています。このような背景から、企業がSNS上で情報を発信しなければ、そもそも認知すらされないという状況になってきており、SNSは“企業と就活生をつなぐ最初の接点”となっています。
企業カルチャーを“見せる”ことで差別化
求人広告や採用ページでは伝えきれない企業の個性、たとえば「上司との距離感」「オフィスの雰囲気」「社員同士のコミュニケーション」などを、SNSはビジュアルや動画を通してダイレクトに伝えることができます。Z世代は、条件や待遇以上に「どんな人とどんな場所で働くのか」に価値を置いており、それが自分とマッチしているかどうかで応募意欲が左右されます。したがって、SNSは企業ブランディングを“視覚化”するツールとして、今後さらに欠かせない存在となります。
採用活動とブランディングを同時に実現
SNS採用の最大の特長は、単に人材を募集するだけでなく、「企業そのもののブランド価値」を高めることができる点です。採用期間中に投稿する情報が、応募者だけでなく将来的な取引先、顧客、パートナー候補などにも届くことで、多角的な信頼の獲得につながります。また、定期的な投稿によって“会社の今”を外部に伝えることは、働く社員にとってのエンゲージメント向上にも効果を発揮します。採用と広報が一体化するSNS運用は、まさにこれからの企業成長において最も合理的な投資といえるでしょう。
SNS採用のメリットとデメリット
SNS採用の主なメリット
SNSを活用した新卒採用には、採用コストの削減、企業ブランディングの強化、カルチャーマッチした人材の獲得といった多くのメリットがあります。求人媒体を使わずに広範囲へリーチ可能で、”今”転職や就職を考えていない層にもアプローチできる点も特筆すべき利点です。
メリット:広告費を抑えて拡散できる
SNS採用は、求人サイトや紙媒体に広告を出すよりも圧倒的に費用対効果が高い手法です。アカウント運用やコンテンツ制作に多少の労力はかかりますが、継続的な発信により“無料または低コスト”でフォロワー(潜在応募者)にリーチできる環境を作ることができます。さらに、良質な投稿はシェア・保存・拡散されることで、企業の魅力が自然に広がり、想定以上の応募効果を生むケースも少なくありません。SNS運用により、「広告を出し続けないと反応が止まる」という従来型の広告依存から脱却できるのです。
メリット:カルチャーマッチした応募が集まる
SNSを通じて企業カルチャーを継続的に発信することで、価値観や社風に共感する人材が自然と集まるようになります。これにより、入社後のギャップが小さくなり、早期離職の防止にもつながります。特にZ世代は「やりがい」や「人間関係」を重視する傾向が強く、投稿から感じ取れる雰囲気や社員の言葉が、応募の意思決定に大きく影響します。エスキューの支援事例では、SNSで応募してきた新卒者の定着率が、求人サイト経由の2倍近く高かったケースもあります。
SNS採用に伴うリスクとデメリット
一方で、SNSは情報発信の速さと拡散性から、誤った表現による炎上リスクや、投稿の継続性・戦略性の欠如がブランド価値を損なう可能性も孕んでいます。明確なガイドライン策定と定期的な見直しが必要です。
デメリット:炎上リスクと発信責任
一方で、SNS採用には明確なリスクも存在します。誤解を招く表現、不適切な投稿、あるいは社員の不用意なコメントによって、企業の評判が一瞬で傷ついてしまう「炎上」の危険性があります。また、投稿内容の正確性や著作権配慮、個人情報保護など、細かな配慮も必要となります。これらに対応するには、SNS運用ガイドラインの策定、投稿前のチェック体制、社内での研修など、リスクマネジメントの視点が不可欠です。ただし、こうした管理体制を整えれば、リスクを抑えつつSNSのメリットを十分に活かすことができます。
新卒採用でのSNSの活用方法
母集団形成と認知度向上
就活生が企業の存在を知るきっかけの一つとしてSNSが活用されることが増えています。エスキューでは、魅力的な投稿コンテンツによって企業の認知を広げ、母集団形成に貢献する支援を行っています。
人柄を見極めるための情報収集
SNSは応募者にとっても企業を見極める重要な情報源です。動画や写真を通じて働く人の表情、雰囲気、チームワークなどが伝わり、入社後のミスマッチを防ぐことができます。
認知拡大のためのコンテンツ設計
SNSは情報発信ツールであると同時に「認知拡大メディア」としても優秀です。特にInstagramやTikTokのアルゴリズムは、非フォロワーにも投稿を届ける仕組みがあるため、コンテンツの魅力次第で爆発的な拡散を狙うことが可能です。新卒採用においては、選考情報だけでなく、社員の日常や会社の雰囲気をテーマにした“共感型”のコンテンツが効果的です。エスキューでは、企画立案から撮影、編集までワンストップで支援し、採用広報に最適な「認知→興味→行動」の導線づくりを行っています。
社員インタビューや一日密着動画で信頼感を醸成
応募者が企業に対して抱く“信頼感”や“親しみ”は、入社意思を大きく左右します。特に、社員の本音やライフスタイルが垣間見える動画コンテンツは、就活生からの反応が非常に良いです。InstagramのリールやYouTube、TikTokなどを活用して、若手社員の「入社理由」や「一日の過ごし方」などを発信することで、「自分もこんな風に働けそう」と感じてもらえるきっかけになります。リアルな声が届く投稿こそ、採用成功の鍵です。
エントリーフォームや採用ページとの導線設計
SNSの目的はあくまで“接点作り”です。興味を持ってくれた就活生を、スムーズに応募アクションへ導くためには、プロフィール欄や投稿文に適切なリンクを設けたり、ストーリーズのリンク機能などを活用することが重要です。加えて、SNSの世界観と採用ページのデザインやメッセージが一貫していれば、離脱率を大きく下げることができます。エスキューでは、投稿設計だけでなく、採用導線まで含めたトータル設計を支援しています。
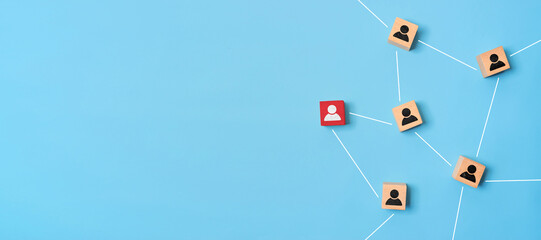
SNSプラットフォームの特性と選び方
X(旧Twitter)の特性と活用法
速報性が高く、イベントや会社説明会の告知、採用広報のリアルタイム配信に向いています。また、就活ハッシュタグを活用した拡散力も大きな魅力です。
Instagramの特性と活用法
視覚的に魅せる投稿が得意なInstagramは、社員紹介やオフィスの様子、仕事風景などを発信しやすく、企業カルチャーの可視化に適しています。
YouTubeの特性と活用法
会社説明会やインターンの様子、社員インタビューなどを長尺で伝えられる媒体で、企業理解を深めてもらう場として有効です。
TikTokの特性と活用法
若年層との接点を作りやすく、親しみやすさとバズの可能性を両立できるメディアです。社員の日常や軽快な動画コンテンツが人気を集めやすいです。
成功事例から学ぶSNS採用の実践
Instagramを活用した成功事例
美容業界のある企業では、社員の働く様子やオフの表情を積極的にInstagramで発信。求職者から「雰囲気が良さそう」「親近感がある」といった声が多数寄せられ、エントリー数が前年の2.8倍になりました。
YouTubeを活用した成功事例
IT業界のベンチャー企業がYouTubeで新卒向けのQ&A動画を配信した結果、就活生からの企業理解が深まり、説明会参加者の内定承諾率が大きく向上しました。
TikTokを活用した成功事例
飲食チェーンがTikTokで店長や若手社員の”1日密着”動画を投稿。学生との距離感が近づき、動画投稿からわずか1週間で30名以上のエントリーがありました。
SNS採用を成功させるためのポイント
ターゲットを明確にする
SNS投稿はターゲットを意識した設計が不可欠です。どの年齢層・属性に響かせたいのかを明確にすることで、コンテンツの内容や投稿時間、使用するハッシュタグが変わります。
コンテンツの質を高める
クオリティの高い画像や動画、コピーライティングは信頼感を醸成します。視聴者の関心を引き、シェアされやすい構成にすることで、自然なリーチ拡大を狙えます。
継続的な情報発信の重要性
単発の投稿ではなく、一定のペースで更新を続けることで企業の”今”を届けることができ、求職者の興味を維持し続けることが可能です。
採用ターゲットを明確に設定する
SNS採用のスタートラインは「誰に見てほしいのか」を明確にすることです。新卒採用の場合、年齢層はおおよそ18歳〜24歳。ですが、文系・理系、地方・都市部、志向性(安定志向か成長志向か)など、属性により響く表現や媒体は大きく異なります。たとえば、感性重視の文系学生にはInstagramやTikTokが有効であり、情報重視の理系学生にはYouTubeやX(旧Twitter)のほうが適しています。エスキューでは、ペルソナ設計から各プラットフォームに最適化した投稿設計まで、一貫したターゲティング支援を行っています。
投稿コンテンツに一貫性と魅力を持たせる
一度見て終わるような投稿ではなく、「この企業の投稿はいつも興味深い」と感じてもらうためには、一貫したトーン&マナーが重要です。写真のテイストや文字フォント、言葉遣い、投稿の曜日・時間帯まで含めて世界観を統一し、ブランディングとしての魅力を構築していくことが、エンゲージメントの高いファン層を形成するコツです。就活生は日々多くの情報に触れているため、選ばれる企業になるには、「見た目の統一感」と「発信内容の信頼感」の両立が必要不可欠です。
社内体制と運用ルールを整備する
SNS採用を一時的な施策で終わらせないためには、運用担当者の明確化、承認フローの整備、投稿スケジュールの設計といった“運用の仕組み”を社内に根づかせる必要があります。特に新卒採用は年度ごとの計画が重要なため、企業カレンダーとSNSスケジュールを連動させておくことが望ましいです。また、社員が自発的にコンテンツ作りに関与できる仕組みや、エンゲージメントに応じた社内表彰制度などを取り入れると、企業全体でSNS採用を前向きに推進できるようになります。
SNS採用における失敗事例とその対策
投稿頻度が低い場合の影響
「アカウントはあるが投稿が止まっている」状態は、企業活動が停滞している印象を与えかねません。コンテンツ作成の外注やスケジューリングツールの活用で投稿頻度を確保することが対策となります。
ターゲット層とのミスマッチ
発信している内容と求職者の興味がずれている場合、期待した効果が得られません。事前にペルソナ設計を行い、コンテンツを調整することが求められます。
社員が映った写真の許可を取らずトラブルに
SNS投稿でよくある失敗のひとつが、社員の顔写真を無断で投稿し、本人やその家族からクレームを受けるというケースです。とくにZ世代は「プライベートな画像を勝手に出されたくない」という意識が強く、許可の取り方が曖昧なままだと、採用広報どころか社内の信頼関係にまで影響を及ぼします。エスキューでは、投稿前に同意を得るためのチェックリストや承諾書の雛形を提供し、企業が安心して発信できる体制を整備しています。
投稿頻度が不安定で信頼感を損ねた事例
投稿が一時的に集中し、その後ぱったりと更新が止まってしまった場合、SNSのアカウントは“廃業状態”のように見られてしまいます。特に新卒採用で見られやすいのが、募集シーズンにだけSNSを活用し、オフシーズンは何の情報も発信しないという状況です。このような状態は「活動していない会社なのかも」という誤解を生みかねません。成功する企業は年間を通してSNSを運用し、非募集期も日常投稿で関心を維持しています。
ターゲットとのズレた内容で応募が来なかった
「若者向けに発信しているつもり」が、実際には中高年向けのトーンだったという事例もあります。たとえば、文字量が多く専門用語ばかりの投稿は、Z世代には“読まれない”コンテンツとなってしまいます。また、画像が暗い、言葉が堅い、ユーモアがないといった点もミスマッチの要因です。投稿前には第三者のレビューを入れ、客観的に“誰に響くか”を検証することが欠かせません。
SNS採用の法務・倫理的考慮
個人情報保護と著作権の重要性
動画や画像に登場する人物の許可取得、BGMや画像素材の著作権管理は、SNS運用において基本的な配慮です。法務担当者と連携しながら慎重に進める必要があります。
炎上リスクへの備え
万が一の投稿トラブルや誤解が発生した場合に備え、迅速な対応体制と社内マニュアルの整備が不可欠です。炎上回避のためには、常に第三者目線でのチェックが大切です。
肖像権・著作権を侵害しないためのルール整備
SNSで使用する画像・動画・音声などには、すべて「利用する権利」が伴います。フリー素材を使ったつもりでも、利用範囲が商用NGだったケースや、背景に映り込んだ人物の許諾を得ていなかったなどのトラブルは後を絶ちません。企業がSNS採用を行う際には、法務チェック体制の構築、社員や外部モデルとの契約締結、社内運用ルールの明文化が必要です。万が一のトラブルを未然に防ぐためにも、社内外の法的リスクを見落とさない体制づくりが求められます。
個人情報の取り扱いと採用投稿の注意点
SNSでは、就活生からのDMやコメントを通じて、個人情報に接する機会も増加します。たとえば、応募者の名前、出身校、アカウント情報などを不用意に晒してしまうと、重大なプライバシー侵害になりかねません。また、やり取り内容を社内で共有する場合でも、管理体制や同意取得の手続きが重要です。採用業務とSNS運用を分けず、情報管理全体を一元化して対処することが、SNS採用の信頼性を高める第一歩です。
炎上時の対応フローと緊急体制の準備
SNSには「発信力」と同時に「拡散力」という両刃の剣が存在します。不適切な表現やミス投稿があった際、すぐに削除して謝罪を出せるかどうかは、企業の評価に大きく関わります。想定問答集の準備や緊急時の広報責任者の設置、削除基準の策定などは、企業がSNSを継続して運用するうえで欠かせない安全網となります。エスキューでは、投稿前のチェック体制や炎上リスク診断も含めた包括的な運用マニュアルを提供しています。
SNS採用の今後の展望
テクノロジーの進化とSNS採用の未来
今後はAIによるレコメンド投稿や、チャットボットによるエントリー受付、分析ツールによる最適化など、SNS採用の自動化が進展していくでしょう。人間とテクノロジーの共創によって、採用精度はさらに高まると見られています。
新たなプラットフォームの登場と影響
ThreadsやLINE VOOMなど、新たなSNSプラットフォームの登場により、採用活動の選択肢も広がっています。早期に対応し、先手を打つことで競合との差別化が可能になります。
AIによる投稿支援と採用オートメーションの進化
SNS採用の現場では、すでにAIの導入が進んでいます。たとえば、ChatGPTを使った投稿文案の自動生成、Canvaによるデザインテンプレートの活用、Chatbotによる応募前対応などは、多くの企業で採用されています。今後は、応募者の行動データをもとに、AIが最適な投稿タイミングや内容を提案し、人事担当者の負担を軽減しつつ、採用効果を最大化する「オートメーションSNS採用」が主流になるでしょう。
新しいSNSプラットフォームへの適応力が鍵に
SNS市場は常に進化しています。InstagramやX、TikTokに続いて、ThreadsやLINE VOOMなど新しいプラットフォームが次々と登場しており、どの媒体にリソースを投下すべきか、柔軟な判断が求められています。特に若年層がどこに“集まっているか”を敏感に察知し、企業として最適なメディアミックスを実践することが、競合との差を生む決定的要素になります。
採用だけでなく定着・教育への拡張可能性
SNSの活用は「採用」だけでなく「入社後」にも広がっています。たとえば、新卒社員向けの社内情報共有や、業務マニュアルの動画化による教育など、SNS的な発想がオンボーディングや定着支援にも応用され始めています。また、企業のSNSに社員が自主的に関与することで、愛社精神やチームの結束力も高まりやすくなります。これからは「採用SNS」から「企業カルチャーSNS」への進化が求められる時代です。

まとめと次のステップ
SNSは今や、新卒採用において欠かすことのできない最重要ツールのひとつです。従来の求人媒体や合同説明会だけでは伝えきれなかった、企業のリアルな空気感やカルチャー、働く人々の価値観を、ダイレクトに発信できるのがSNSの最大の魅力です。特にZ世代は、「自分らしく働けるか」「その会社の考え方に共感できるか」といった内面的な価値観を重視する傾向があり、SNSを通じて得た情報こそが、応募のきっかけや意思決定の材料になっています。
つまり、SNSは単なる採用告知の手段ではなく、**企業のブランド価値を伝え、共感を呼び起こし、未来の仲間と出会うための“入口”であり、“架け橋”**でもあるのです。魅力的なコンテンツを発信し続けることで、企業の存在に気づいてもらい、興味を持ち、ファンになり、最終的には応募・入社というゴールに導くことができます。
私たち「エスキュー」(東京都渋谷区)は、こうしたSNS採用の本質を踏まえたうえで、企業ごとの採用課題や業種特性に合わせたオーダーメイド型のSNS運用支援を行っております。企画立案から撮影・編集、投稿代行、運用分析、改善提案までを一気通貫で対応し、社内リソースの負担を最小限に抑えながら、最大限の成果を生み出します。
また、当社のプランナーチームは、行動心理学やブランディング、インフルエンサーマーケティングに精通しており、Z世代の心を動かす“伝え方”にこだわり抜いたクリエイティブを提供。建設、IT、美容、飲食、物流など、あらゆる業界での豊富な実績に裏打ちされたノウハウをもとに、再現性の高いSNS採用戦略を構築いたします。
「何を投稿していいか分からない」「更新が止まってしまっている」「思うように応募が集まらない」など、どんなお悩みでも構いません。SNS採用を強化したいとお考えの企業様は、ぜひ一度、私たちエスキューへご相談ください。御社の魅力を正しく・効果的に届ける仕組みを、私たちが全力でサポートいたします。